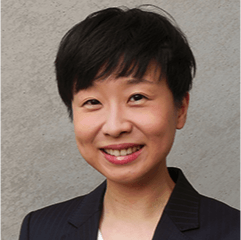一人芝居「マリヤの賛歌―石の叫び」は慰安婦体験をもとにした城田すず子の自伝『マリヤの賛歌』を原案に、くるみざわしんが戯曲を執筆し、岩崎正裕が演出、金子順子が出演した作品である。2022年の初演を経て各地で上演を続けており、戦時性暴力の構造的な問題を、現代社会の抑圧構造と地続きのものとして描き出している。
2025年9月15日、一心寺シアター倶楽で観客としてこの上演に立ち会った時、強く印象に残ったのは、創作者たちが「城田すず子」という存在と向き合う際の真摯で注意深いまなざし、そしてその言葉を観客に手渡す時の慎重な手つきだった。
言葉を「伝える」こと
登場人物は「私 『マリヤの賛歌』を繰り返し読む女」ひとり。「私」は、城田が東京下町の比較的裕福な家に生まれたことや、家の借金を返すために芸者屋に奉公し、海軍御用達の台湾の遊郭や南洋諸島の慰安所で働くようになった経緯を語る。語りは『マリヤの賛歌』を読む形で進められ、「私」は城田が戦後に占領軍向けの慰安所で働いたこと、婦人保護施設に身を寄せ、神への祈りと出会ったこと、戦地での体験を語り始めたこと、と語り進めつつ、城田の言葉と「私」の思考の狭間で揺れ動き、葛藤する。やがて「私」は戦争が女を「無垢な女」と「汚れている女」に二分する構造の問題に気づき、その二分する態度が自分自身の中にもあることと向き合う。
金子の表現は、城田の言葉と慎重に対峙した時の「私」の心の揺らぎを観客に向けて伝えていた。舞台上の「私」は、語り手であると同時に城田の言葉の聴き手でもある。城田の言葉を媒介することで、観客に「この声をどう聴くか」を問いかける。その距離の取り方は、当事者の痛みを容易に代弁しないための倫理であり、劇場空間には、問いを考えるための時空間が綿密に構築されていた。
観客の位置づけ-「青みどろの沼」と「あわれみの池」
舞台美術は最小限であった。机と椅子、机の上には『マリヤの賛歌』と「石」。基本的に照明と音響も控えめで、舞台と客席は「観られる-観る」の区分の中に収まっている。だが、その区分を乗り越えて二度、客席に光が届く場面があった。
第1景「私の部屋」で、「私」は、慰安婦として死に、世間から見えないものとされてきた女性たちを想い、次の台詞を言う。
私は目を伏せる。動きを止める。気づかれるのが怖い。傷は痛んで、腐って、肉が崩れ、足元から沼が広がってゆく。たくさんの女が日の当たらない沼の底に、口を失い、かたまっている。身を寄せて集まったわけじゃない。何かの都合で集められて帰れず、死んでここに放りこまれた。女たちを集めた「何かの都合」は生き延びている。(1)
女性たちを日の当たらない沼の底に集めた「何かの都合」を告発するこの言葉が語られている時、客席全体が薄青い光に照らされる。その演出は、観客を「沼」として見立てているかのようであった。沼は女たちの肉が腐ってできたものであり、女たちを閉じ込める檻でもある。その沼との同一視は、普段見えていない「女たち」の気配を観客席に生じさせる。
そして終盤、第11景「祈り-復活祭の夜」で、再び客席に薄青い光が当たる。この景で「私」は、城田が人生の終盤に安心して暮らせる保護施設に入った後も、自分の過去を理由に差別を受ける悲しみや悔しさの中にいたこと、しかし神に祈ることで励まされ、詩を書いたことを観客に伝える。その詩の一部は次のようである。
私はアダム以来の/わるい代表の蛇です/私はその長い間の汚名をなくすため/主にあわれみを乞いました/涙を流し長いからだをまるめ/青みどろの沼からぬけ出すため/主にあわれみを乞いました/主はおっしゃいました
そんなに一生懸命ならば/私はあなたにあわれみの池をあたえましょう/友が集まって来るでしょう/長い間の汚名をなくすために/一つ一つのうろこの間にしみている/沼のにおいを消すために(2)
ここで語られる「青みどろの沼」という言葉は、第1景で「私」が語った「日の当たらない沼」を思い出させるものである。詩はその沼から抜け出すために神が「あわれみの池」を与える、と続くのだが、それらの言葉が紡がれている時に、観客席が薄青く照らされる。この時、観客席は「あわれみの池」として見立てられているようであった。
青い光は観客席を舞台上の世界に一体化させ、舞台上の出来事は人ごとではないのだと静かに観客に伝えていた。「青みどろの沼」ではなく「あわれみの池」として存在するためには、どうしたら良いのか?そう問いかけているように感じた。
ラジオの声と観客のリスナー化
上演の終盤の忘れられない場面は、「私」が城田のラジオ放送での証言を巡る語りをする場面である。城田は、慰安婦として戦地で性の提供をさせられた女性たちの凄惨な状況、状態を1985年のラジオ放送で語った。その様子を、「私」はそれまでの抑制した語りではなく、そこに城田が居るかのような存在感で身体化した。「私」が向き合っているものが、自伝の「文章」からラジオが伝える「声」に変わったということが、変化の背景にあるのかもしれない。
「声」は文章よりも直接的に声の主の存在を訴える。その「声」は、想像していたよりもどっしりとした、強さと芯のある声で、城田の人生の重たさを感じさせるものであった。その重たさに、強く感情が揺れた。その時、観客は1985年の放送を聴いていたリスナーの一人となっていたのかもしれない。当時のリスナーの中には、ラジオ放送を聴いて城田に寄付をした人々がおり、城田は集まった寄付で慰安婦の鎮魂碑を建てたという。寄付という実際の行動に移るほど、当時のリスナーの心は激しく揺さぶられたのだろう。そして、観客席に居た私の心の中にも、その現象が生じたように感じた。
受け渡された後は
本公演は、城田すず子の言葉を奪うことなく、注意深く伝えようと試みていた。舞台上の「私」は、当事者の声を代弁することを避けながら、その痛みと祈りを観客に手渡し、慎重に編まれた語りと薄青い光は、観客にそれぞれの立ち位置を問いかけた。
城田の声をどう受け止められるのか、どうその声を可視化できるのか。そして、女性を二分して戦争による性被害を不可視化しようとする社会構造をどう変えていけるのか。観た後に考えることは尽きない。私に何ができるのだろうか、と。
注
(1)原案城田すず子、作くるみざわしん『マリヤの賛歌-石の叫び』1頁(劇場販売用の上演台本)。
(2)同上、9頁。本来の詩ではスラッシュ部分で行が変わっている。
主な参考文献
原案城田すず子、作くるみざわしん『マリヤの賛歌-石の叫び』(劇場販売用の上演台本)。
城田すず子『マリヤの賛歌(Kindle版)』岩波書店、2025。