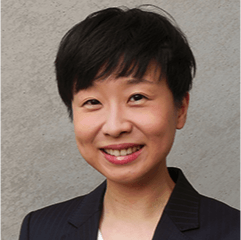繰り返し、祝祭空間を立ち上げる
三重県総合文化センターの巨大な建物の裏手に、木が茂り小川が流れる日本庭園がひっそりとある。そこに仮設された野外舞台で、烏丸ストロークロック(以下・烏丸)が『祝・祝日』を上演した。(11月14日、三重県津市の三重県総合文化センターのフレンテみえ裏日本庭園で所見。柳沼昭徳構成・テキスト・演出。)これは「日本に残る祭りや神楽を研究し、実際に体現してみる(1) 」継続的な活動で、2018年に宮城で初演した後、広島や兵庫、京都、三重、沖縄と再演を重ね、今回が初めての野外公演となる。公演会場にはのぼりが立ち、篝火がたかれ、唐揚げやポテトフライの販売もあり、小さな祝祭空間となっていた。
山伏的媒介者に、俳優がなる
烏丸の劇作・演出担当の柳沼昭徳は、2015年に東日本大震災を背景とした作品『新・内山』を創る際に神楽に出会って以降、作品に間接的、直接的に神楽の要素を取り込んできた。特に東北に分布する山岳信仰や修験道に源流を持つ山伏神楽や法印神楽に取り組んでおり、山の神と人を繋ぐ媒介者である山伏の精神や身体性を知るために、2018年には俳優陣が山伏の体験修行にも参加をしている。神楽の形態を習得し模倣することが目的ではなく、神楽の哲学を身体化・内面化することで、細分化され孤立し悩む人の心の拠り所となる表現を舞台で創ろうとしている。(2)
人ならざる者を呼び起こし、連帯する
今回は岩手県に伝わる早池峰神楽の式舞から「鶏舞」「三番叟」「八幡舞」「山の神舞」が、荒舞から「諷誦の舞」が選ばれて舞われた。式舞は神楽を奉じるときに最初に舞われる演目で、舞台を清める意味合いを持つ。「諷誦の舞」は龍神が悪神悪鬼を退散させ、四方鎮護、七難即滅を願う舞と言われている。感染症流行の鎮静への願いも感じる演目の選定である。(3)
上演様式は神楽の様式に倣いつつも現代的に再構築されていた。例えば、神楽では舞台奥に神楽幕と呼ばれる幕が張ってあり、その幕をすくいあげて舞い手は登場する。今回もそれは引き継がれており、「鶏舞」では二羽の鶏を演じる者が、「三番叟」ではひょうきんな翁が、「八幡舞」では弓矢で魔を払う者が、「山の神舞」では山の神様が、幕の向こうからやってくる。その一方で、神々を彩る衣装は白やグレーのシンプルな洋服の上に青や赤や黄色の襷をかけて赤い袖を羽織り、黄色や緑で創られた色鮮やかな面をつけるという和洋折衷で、楽器にも和楽器の手平鉦や弓太鼓に加えて洋楽器のチェロが使われていた。奏者が打ち鳴らす小さな手平鉦の金属音が調子を刻む上に、弓太鼓の柔らかな打音やチェロの音が重なる様子は、観客をトランス状態へと誘う。舞台は異界との境目を揺らがし、次第に神―人ならざる者たち―の気配が色濃くなっていく。
最後に舞われた「諷誦の舞」で、空間は変容する。これは跳躍や旋回が多いダイナミックなふりを繰り返す一人舞で、最初は面をつけて神を身に降ろすように舞い、次にその面を外し、体力の限界に挑戦するように舞い続ける。繰り返す度に跳躍は重たさを増し、体の軸もぶれていき、舞い自体の洗練度は落ちて行くが、動き続けることが生み出す熱量が、存在感を増していく。それは人が人ならざる者たちと共存する姿のようでもある。舞台空間は周囲へと開かれ、観客席に居る私の心も人ならざる者と繋がり合っているように感じてくる。
この変化は、五感を使い観ていたからこそ感じられたものでもある。上演は17時に始まるのだが、11月の津市での17時はちょうど陽が落ち、昼から夜に向かう空気の変化が肌で感じられる時刻である。夜風に篝火の音と煙の匂いが主張しはじめ、始まりの気配に気が引き締まる一方で、会場で買った食べ物の匂いが宴の気分を高める。演目を重ねるごとに夜は深まり、舞を観る間にふと見上げた空の上に星の明るさを見つける。五感を舞台に同化させず、常に人ならざるものたちによって異化され続ける中で観たからこそ、連帯感が生まれる気配を感じたのである。
現代化された神楽だからこそ、可能な連帯もある
この現象は神楽一般に生じるものかもしれないが、現代舞台芸術として提示された本公演で生じた点に、特別な意義があるともいえる。なぜなら、神楽は人の営みの中で受け継がれていく芸能であり、伝承されてきた地域と切り離し難い部分があるが、その一方で、人の営みは地域から離れても継続するし、意識的に地域から離れる人も居るからである。本公演は、東北の神楽を舞ってはいるが、東北の風土色が濃いものではないし、津市で舞われてはいるが、津市の色が強いわけでもない。地域と一定の距離が保たれていることで、どこに生きる人でも、気負わずに参加をすることができる。特にこの一年半ほどの間で感染症の広がりを抑えるために家で過ごす時間が増え、物理的に他者との壁が生まれた。行動範囲が制限された分、心の孤立感は深くなっているように思う。誰でも気楽に参加でき、引きこもった心を他者や人以外の存在との連帯の中に解放できる空間は、孤立から抜け出すために、まさに今必要なのである。
心を繋ぎ続ける
烏丸は次回作として、12月末に京都のTHEATRE E9 KYOTOで、2016年から作り続けている『新平和』を上演する。広島の原爆を取り上げた作品で、ここにも神楽の精神が生かされているという。ちかごろは、感染症関連の問題が取り上げられることが多く、対照的に他の問題に関する議論が減少したが、社会や歴史が抱える問題が解決したわけではない。『祝・祝日』で人ならざる者を呼び降ろした烏丸は、次回はどのような空間を立ちあげ、何と観客とを繋ぎ合わせるのだろうか。
1 「烏丸ストロークロックと祭 祝・祝日」(https://shukushuku.karasuma69.org/)2021年11月23日閲覧。
2 柳沼昭徳「混淆を知る」「伝統芸能アーカイブ&リサーチオフィス」(http://traditional-arts.org/report/2019/08/02/697/)2021年11月23日閲覧。
3 当日配布パンフレットを参照