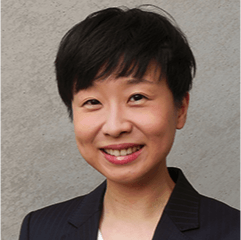舞台の闇から差し上げられた手の平が、死者の手招きのようにリズムを刻む。そこから約60分間、サファリ・Pの俳優たちの身体が、生と死の狭間の魂の彷徨を表現する。劇作家・演出家の山口茜は、アルバニア高地の伝統的な慣習法「掟(カヌン)」の中で生きる人を描いた作家イスマイル・カダレの小説『砕かれた四月』の筋を引き継ぎながら、オリジナルの『透き間』の劇世界を立ち上げた。(2022年3月4日と5日に京都府立文化芸術会館で観劇、上演台本・演出=山口茜)
カダレとの出会い
劇団がカダレの小説の舞台化に取り組む発端は、2019年6月にコソボ共和国の芸術祭FemArt Festival 7thに参加し、アゴタ・クリストフの『悪童日記』を上演した時に遡る。それ以降、本作に至るまで3回、創作過程を公開する企画を立てた。2020年2月にコソボ公演の報告会を行い、2020年12月にワーク・イン・プログレスを開催して学習会やコソボ紛争を生きた人たちへの聞き取りを行った様子を紹介し、2021年1月にはTHEATRE E9 KYOTOで『「砕かれた四月」―プロトタイプ―』を上演した。
カダレはアルバニアで最も知られた作家であるとはいえ、日本で名前が知られているとはいえない。創作過程の公開は、観客とカダレとの出会いの場を増やし、アルバニアとの心の距離も近づけた。
演劇創作は本番だけでなく、その過程を観客とどう共有するかも重要である。本公演に至るまでの3度の企画は、他者の文化を否定するでも驚愕するでもなく、どう距離をとって向き合うことができるのか、ということを考える材料を観客に提供する、大事な役割を担っていたように思う。
小説との差異
さて、山口はどのようにカダレの小説から発展させて、自分の世界を組み立てていったのだろうか。
カダレの小説はアルバニア北部の高地が舞台で、血族が殺されたら一族の男が殺人者を殺さなければならないという掟、「血の確執(ジャクマリャ)」の遂行を巡る話である。べリシャ家のジョルグがクリュエチュチェ家のゼフを掟に従い殺した3月から始まり、4月にジョルグがクリュエチュチェ家の男に殺される場面で終わるのだが、その間にジョルグの叔母が試みた両家の和平交渉が決裂した過去や、夫に連れられ新婚旅行で高地を訪れたディアナとジョルグとの出会いなどが語られていく。
一方、舞台の大筋は、新婚旅行で来訪した「妻」が、人を殺して復讐の連鎖の中を「歩く人」に出会い、復讐の連鎖を止めようとする、というものだ。しかし「妻」は高地に暮らす「老いた人」や死ぬまで「寝たきりの人」と出会ったり、「寝たきりの人」を侮辱した「夫」が「老いた人」に殺されたりする過程を経て、掟を許容する側に回る。
小説は掟の遂行者のジョルグの視点を軸に進むのだが、舞台では「妻」が重要な役割を担う。彼女は小説の中のディアナや叔母の造形を引き継ぐ人物だが、両者はジョルグの村の外から来訪する人たちである。舞台は「妻」、つまり外部者の視点から切り込むことで、カダレが描く世界と距離を取りつつ、復讐の連鎖と向き合っていた。
もう一人の重要な登場人物は「寝たきりの人」で、山口オリジナルの登場人物である。人を殺そうとして自分の頭に銃弾を撃ち込まれて意識が無いまま眠る人なのだが、『透き間』のチラシの裏面の文章からは、その人の造形には傷痍軍人だった山口の祖父が投影されているようだとわかる。山口の個人的文脈を持つ「寝たきりの人」が組み込まれたことで、「ジャクマリャ」は、アルバニア高地固有の文脈から離されて、日本を含む各国に顕在する「人殺しの連鎖」の問題として再構築された。
掟と人と
山口が描く劇世界を台詞以上に雄弁に語ったのは各俳優の身体である。俳優とダンサーを含むサファリ・Pのパフォーマンス力を生かした身体表現は、物語の情景を描写するだけでなく、抽象的な「掟」の性質を、視覚的に語った。
特に「老いた人」(高杉征司)が、掟の恒常性を「妻」(佐々木ヤス子)に語る場面で、「老いた人」に他3人(達矢、大柴拓磨、芦谷康介)が密着して肉塊を作り、それまで人の姿であったものが一気にグロテクスになる様子は、掟は人が創るということを端的に示すようで秀逸であった。この場面は舞台の最後に繰り返されるのだが、そのときには、「老いた人」の位置に「老いた「妻」」が入り、「妻」の位置には「老いた人」を演じた高杉が「新しい妻」として立つ。それは人が入れ替わりながら掟を創ってきたことをさらに説得力を持って視覚的に語る。
これらの「掟」の表現からは、掟が決して普遍的な存在ではなく、人が創り続けることで継続してきたものだと主張しているように感じられる。人が創るのならば、人がその在り方を変えていけるのではないだろうか。
樫の実を実らせられるか
劇中では掟は変わらないが、復讐の連鎖を止めようとした「妻」の言葉には印象的なものがある。それは「樫の木が枯れていくのを、ただ手をこまねいてみていてはだめ(1)」と始まる。これは小説『砕かれた四月』の中で、和解を主張する叔母が、廃れるべリシャ家を樫の木に例えて語る言葉である。舞台の「妻」はそこに「一枚一枚、葉を手に取り、水を与え、堆肥を加え、陽の光に晒さなくてはならない。そうすればいつか、私達は、私たちの間にポッカリとあいた誤解の穴を、煌く無数の樫の実で埋めることができたのに(2)」という言葉を足した。後悔の言葉の形態を取ってはいるが、これは観客への劇団からのメッセージのように受け取ることもできる。世界を巡る情勢が緊張感を増す今、その言葉が切迫感を持って心に迫ってきた。樫の実を実らせるために、私たちは何をしようか。
(1)山口茜『「透き間」上演台本』合同会社stamp、2022年、10頁
(2)同上、10頁
主な参考資料: イスマイル・カダレ著、平岡敦訳『砕かれた四月』白水社、1995年
山口茜『「透き間」上演台本』合同会社stamp、2022年
『透き間』当日パンフレット
「サファリ・P」ウエブサイト