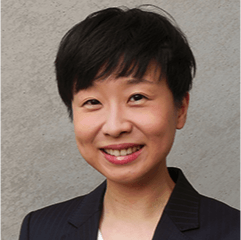9月、JR新今宮駅周辺を中心に、20か所以上の会場で、演劇、ダンス、映画、音楽など複数分野の上演が展開する「路地裏の舞台にようこそ」が開催され、その最後の3日間に、ユニット「野良犬」によって舞台『「月灯の瞬き」~深津篤史短編集~』が上演された。上演場所は、飛田新地から徒歩数分の路地に立つ銭湯「日之出湯」の駐車場2階の居住空間。床の間付の6畳程度の畳敷きの和室が舞台で、和室から続く板の間のキッチンダイニングが主な観客席となっていた。観客は隣の部屋をのぞき込むような形で舞台を鑑賞するのだが、目線の先には窓があり、夜風や時折通る車のライトや話し声が上演空間に入り込む。民家の2階という小さな日常空間に非日常的な瞬間が立ち上がっていく、魅力的な時空間であった。
深津篤史の言葉に抒情の光を当てる
作品は深津篤史の短編戯曲「月灯の瞬き」を軸に短編数編を繋げた構成となっている。桃園会を主宰していた劇作家・演出家の深津は関西に基盤を置いていたが、その魅力は広く知られ、1998年には第42回岸田國士戯曲賞、2006年には2005年度(第13回)読売演劇大賞の優秀演出家賞を受賞し、新国立劇場での仕事もしていた。2014年に46歳の若さで亡くなる間際まで創作を続けたが、短い言葉で紡がれるどこか詩的な台詞や、時折挟まる間、絶妙に曖昧さを残す俳優の演技などが独特の抽象性と雰囲気を生む上演で、あの空気感は、得難いものとして今も記憶に残っている。
今回、『「月灯の瞬き」~深津篤史短編集~』の演出を担当したユニット「野良犬」の森本洋史は、そんな深津の演出助手を務めていた弟子にあたる。師の演出とはまた違う空気感を持つ、抒情のある世界が、深津の言葉を媒介に立ち上げられていった。
交差する日常と非日常
上演は、祭りの夜の20代後半の女性(UTA)と、年上らしい男性(緒方晋)の会話で始まる。女性は男を慕っているが、男性は自分の歳を理由に想いを受け流す。感情をぶつけるUTAと、淀むような存在感を示す緒方の対比が面白い。女性が出ていくと、入れ替わりに落ち着いた雰囲気の女性(木全晶子)が入って来る。木全の自然な演技は場の日常性を高め、他人の生活に入り込んだかのような錯覚を生み出す。
場面が終わると、短編戯曲「月灯の瞬き」をもとにした場面が始まる。北沢(川本三吉)と同棲相手の鹿島(木全晶子)の家の居間が舞台で、時刻は飲み会後の深夜0時。居間には北沢の他に、高田(川村智基)と文(UTA)とが居り、文は北沢が好きで高田は文が好きという複雑な関係性の中で会話が始まる。鹿島と文の間で揺れる北沢の気持ちや、酔いの中で葛藤する高田の想いが漏れ出てくる。
恋に浮かれる三人と対照的な位置に居るのが鹿島である。鹿島は洗濯機を回し、文と高田が帰った後には部屋の片付けをし、日常生活を回していく。酒と恋が持つ非日常的な雰囲気とは異なる目線を作品に持ち込む人物なのだが、今回の上演では、その鹿島が、北沢が文に買った煙草を捨てる場面が良かった。捨てる動作が、ほんの少し強く感じるという小さな違和感なのだが、そこに日常では隠し続けている鹿島の行き場のない苛立ちが見えた。日常に潜む劇的な一瞬/非日常の瞬間が可視化され、記憶に残った。
「月灯の瞬き」の次はまた時空間が変わり、喪服の男性(緒方晋)と女性(木全晶子)が登場する。ラジオドラマ「黄金虫」をもとにした場面で、部屋の隅で死んでいく黄金虫の描写と、人生の終幕に思いを馳せるような台詞が続く。その台詞を聞くうちに、上演を通して耳にしてきた会話が目前の二人の姿に投影されていく。日常と思っていたものが、実はかけがえのない一瞬一瞬であり、非日常的な輝きのあるものであったように見えてくる終幕であり、惹きつけられた。
人と人を繋ぐ-「路地裏の舞台にようこそ」
今回の舞台の演出の森本は、「路地裏の舞台にようこそ」の企画・運営・制作者の一人でもある。企画についても紹介をしておきたい。
この企画は、2021年に3日間の開催期間で立ち上がり、徐々に規模を大きくして今年は8日間での開催となった。開催場所のJR新今宮駅周辺は、具体的には、新世界地域から、西成区の釜ヶ崎エリアやあべのキューズモール裏手あたりまでのことである。日雇い労働者が暮らすドヤ街を含む場所で、釜ヶ崎芸術大学(旧・ココルーム)や、kioku手芸館「たんす」など、創作活動を通して新たな公共の場を創る試みが続けられてきた地域でもある。
この企画はそのような個々の活動とも手を携えている。例えば樋口ミユ(Plant M)が釜ヶ崎芸術大学やひと花センターの協力で創った『路地裏BABY』&『路地裏LADY』の野外上演がその一例だろう。NPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワークの協力で舞台手話通訳が付いていたり、投げ銭制になっていたりと、参加に伴って生じる敷居を下げる工夫が行われた上演でもあった。
樋口は関西小劇場でおなじみの劇作家・演出家だが、他にも髙安美帆(エイチエムピー・シアターカンパニー)、「空の驛舎」、「羊とドラコ」、デカルコ・マリィなど、関西の「ちょっと気になるあの人」の表現に出会えるショーケースのような役割もこの芸術祭は担っている。そのような表現者たちが、おでん屋やカフェやコインランドリーといった街中で上演するので、アーティストと街が出会う場としての意義もある。
上演以外の企画も魅力的で、「ちんどん通信社」のちんどんや「まわしよみ新聞」の陸奥賢の案内による「丑三時ツアー 夜明け前の新世界・てんのじ村」などの、大阪の大衆文化や歴史を楽しめるプログラムもあれば、関東圏から来た庭劇団ペニノのタニノクロウによるバー、竹中香子による演技とハラスメントの関係を探るワークショップ、その竹中が主演し太田信吾が監督をした映画『現代版 城崎にて』などの映画の上映もある。地域や分野を越えたつながりが、この企画の魅力の1つである。 そういう視点で考えると、『「月灯の瞬き」~深津篤史短編集~』の俳優陣も面白い組み合わせである。上演の屋台骨となっていたのは関西を中心に長く活動してきた木全、川本、緒方の三名。木全には写実性と丁寧さが、川本はアウトロー的軽さが、緒方は喜劇的な真面目さがあり、その個性は公共劇団の兵庫県立ピッコロ劇団、野外演劇の劇団犯罪友の会、小劇場演劇のThe Stone Ageという各人が携わってきた分野の個性をどこか思い出させる。そのような屋台骨に、今回は若い世代で今精力的に舞台を創っている「餓鬼の断食」の川村智基と「InorU」のUTAが組み合わさることで、上演に新しい風が吹き込んでいた。関西で活動する演劇人の多層性が感じられる配役である。 どのような人をどのように組み合わせて世界を創るかという点は、演出の大事な仕事だろう。今回の森本の演出の良さのひとつは、この組み合わせ方だともいえるのではないだろうか。
路地裏で混ざる日常/非日常
路地は、住人が家の前の道に椅子を置いて座ったりできる、公私が混ざる縁側のような空間である。飲み屋やカフェや銭湯では外部からの訪問者を受け入れたり、当初は訪問者であった人が常連となり飲み屋のカウンターの中で手伝ったりもする。容易く反転する主人と客人、住人と訪問者の間柄は、客として観ていたらいつのまにか創る側に居た、という事例が珍しくない小劇場演劇界隈に特有の間口の広さとつながる側面もある。
「路地裏の舞台にようこそ」はそんな間口の広さを体感できる企画であり、その中の『「月灯の瞬き」~深津篤史短編集~』は、つながりあって創作を重ねてきた関西小劇場界だからこそ立ち上げられた時空間であると言えるかもしれない。