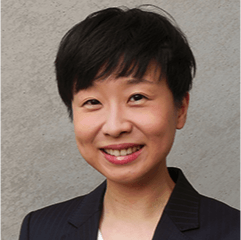プロトテアトル第11回公演『レディカンヴァセイション(リライト)』は、地震で崩れた山奥の廃ビルの中で身動きがとれなくなった人達が、暗闇の中で雑談を続けながら救助を待つ会話劇である(2022年6月11日14時の回を、兵庫県伊丹市のアイホールで観劇。作・演出:FOペレイラ宏一朗)。登場人物は、廃ビルの警備のアルバイトをする2人、大学生のサークルメンバーの4人、掲示板で知り合った自殺志願者の4人と、その掲示板にメンバー募集のメッセージを書き込んだ1人。異なる事情で廃ビルに来て瓦礫に埋まってしまった11人が、建物が崩壊する毎に下層階へと移動し、地下室までたどりつくという筋を持つ。舞台面は、可動式の床を持つアイホールの劇場機構を生かして四角く陥没させられており、その空間の上に巨大な斜めの板が斜めに吊り下げられてあった。その空間が持つ圧迫感と陥没感は、崩れた廃ビルが持つ不安定さを醸し出す。高い天井が作るホールの広い空間をあえて区切って狭く利用した点が、登場人物たちの孤立感を感じさせて効果的だった。
心の闇を可視化する
台詞の応酬で進む劇なのだが、劇中で最も印象に残った場面は台詞ではなく劇終盤の長い暗闇であった。その場面に至るまでに、登場人物が居る虚構世界と俳優の肉体がある劇場空間、観客が暮らす劇場外の現実世界を台詞が徐々に結び合わせていく。
例えば、第1場でビル中腹に埋まっている警備員の場面。真面目な雰囲気の志村(友井田亮)と遊び人風味の安達(宇垣サグ)の絶妙なテンポのかけあい漫才に引き込まれる場面だが、トランシーバーで助けを求めようという安達に志村が「基本的にはここの警備を発注している会社も、受注している会社も、表向きには関わってない形になってるから、そういった外との連絡手段ないんだよ(1)」と教える。仕事を細分化し、責任の所在を不明瞭にしながら遂行されていく「何か」があることが示唆され、現代社会の闇を連想させる。
第2場では、ビル上部で埋まっている大学生のサークルメンバーの一人の田崎(大月航)が、もっと揺れたらビルが液状化現象を起こし溶解して動けるようになるかも、と考え「何か因果関係があるかもしれないですよね。俺が揺れたら地球?が揺れる?(2)」と言って埋まったまま猛烈に揺れ始める。田崎の動きの振り切った激しさは観客の笑いを誘発するが、その台詞は「廃ビル」の状態と登場人物の行動とが何かの因果関係を持つ可能性を暗示し、観客の想像力を膨らますトリガーともなる。
その可能性は第3場でひとつのイメージに焦点を結ぶ。ビル下部で閉じ込められた自殺志望者の4人の会話の場面で、死に心の救済を求める一方で生きるための救助を待つという人の心の複雑さが読み取れる場だが、そこで掲示板にスレッドを立てて集合場所を決めた鍵となる人物が「ホーリーさん」で、ホーリーさんだけは待ち合わせに来なかったとわかる。会話の中でも気になってくるのは、場所指定もした発起人なのに待ち合わせ場所に居ないという違和感と、待ち合わせの時間に揺れがきてビルが崩れたという不思議な一致である。劇世界の中では偶然の一致で処理できる部分だが、先ほどの田崎の言葉「俺が揺れたら地球?が揺れる?」を補助線とすると、劇の世界が登場人物、特にホーリーさんの心の状況と呼応する場のようにも感じられてくる。心の状況と関係すると考えると、ホーリーさんと他の4人が異なる場所に居る理由も推察できるような気もしてくる。
それ以降、劇は上層階から最下層の地下駐車場へビルの瓦礫と一緒に滑り落ちていく人達の様子を描き、様々な事情を抱えた人達が出会って会話し、最終場で互いに本名を名乗り合う場面で終わる。先述した印象的な暗闇は、その最終場でホーリーさんが他者に心を開くことが出来ない時に作られる。客席から舞台面を見下ろすまま長い暗転に入ると平衡感覚が少し狂い、まるで自分が斜面の上に居て、暗闇に引き込まれそうな錯覚に陥る。救済と称して集団自殺を企画するホーリーさんの心の暗さに、観客席が巻き込まれたように感じた。台詞と俳優の力演と劇場空間、その他照明音響全てを効果的に用いて観客の感覚を巻き込んでいき、劇場全体で闇を感じる時空間を創り出した、その手つきの丁寧さが印象的な上演であった。
「祈り」の舞台
コロナ禍で対面での会話が制限される時間が増え、各地で世界の複雑さが可視化して暴力が目立つ現在、本作の主題である「会話」の重要性は増している。この劇は、「ホーリーさん」が自分の本名の「木曾伸之介」を名乗ることができたタイミングで終わり、その時ホーリーさんの心の闇に差し込む光のように舞台装置の上部から光が射しこみ、徐々に空間が明るくなるという綺麗な結末を持つ。美しすぎるようにも感じられるのだが、チラシ裏側に「祈りにも似た、希望を内包する会話の劇」とあるように、この劇は、現実がこうであるという提示ではなく、こうあってほしい、つまり「会話で人が救われてほしい」と願う理想を描く。救済のめどがつかない崩れた廃ビルの中に居てもなお、会話を続けて目前の人と分かり合おうとする努力を続ける登場人物たちの在り方は、会話の困難さを知る今だからこそ観客の心を癒し、励ます。
「わかりやすい表現」の是非
その上で気になったのは、人物造形や台詞がどこかステレオタイプ的である点である。例えば、最終場で冬馬がいじめられていた過去を語り出す時の台詞では、いじめがエスカレートした経緯はわかるのだが、冬馬の肌感覚が感じられない。冬馬はどこで暮らしているのだろうか。空気の綺麗な山際だろうか、高いビルが並ぶビジネス街なのか、工場の機械音が響く下町なのか。「高校生でいじめを受けた人」という以外の登場人物の人生の在り方が見えてこなかった。苦しみや悩みは個人的なものであり、他者の苦しみを共有することは難しいだろう。だからこそ本作では言葉を尽くして会話をする重要性を示しているのだと思うが、それならば、冬馬の、そしてほかの登場人物たちの個性が台詞から感じられる方が、劇のメッセージの説得力は増す。
もう一点、劇のわかりやすさをどう捉えるか、ということも考えてみてほしい。本作は非常にわかりやすく、それは良いことではあるが、観客が想像する余白が奪われているとも考えられる。台詞の中でつじつまがあうように会話を構築する必要は必ずしもない。創作者側の意図があれば、観客の理解が追い付かないような言葉選びをしても良いし、論理で説明されない空白部分は、観客の想像力が補うだろう。むしろその方が、観客の心の能動性が増すかもしれない。観客を信頼して解釈をゆだね、観客の心と会話を繰り返すための「曖昧さ」があっても良いのではないだろうか。
一方で、記号的な人物像は喜劇性とは相性が良い。笑いを誘う部分の台詞回しは秀逸で、それを演じる俳優たちの力演もあり、魅力的な場面が数多くあった。前述した第1場の志村と安達の掛け合いもそうであるし、第2場では大学生サークルの4人、田崎(大月航)、島田(吉田和樹)、大溝(豊島祐貴)、横井(塗木愛)が、「埋まっている」という身体演技の可能性が限定された状況で、台詞で見事に喜劇性を発揮していた。自殺志願者の藤村(石川信子)、夏目(大江雅子)、堺(岡田望)、冬馬(有川水紀)も、絶妙な間を活用して場の空気感を形成していた。中でも結婚詐欺師にだまされた夏目は、いびつな恋心を表現しつつ、元結婚詐欺師でもあった安達との掛け合いを軽快に展開して人々の緊張を緩ませていた。喜劇的ではないが、ホーリーさん(浜田渉)の独特な佇まいも不気味さを醸して印象的だった。小道具も大道具もほぼない空間で、喜劇性を担保しつつ極限状態の中の人たちを表現し続けた俳優の力を感じる公演でもあった。
本作は2015年に20分の短編として書かれ、2019年に長編として改訂したものを、更に改訂したものだという。2015年の時は大学生のサークルの4人の話で、大地震で崩落したビルの中で一人が負傷し死の気配が漂う中で会話を続けるという具象的な描写がある終幕であった。2019年の再演時は、今回の形とおおむね似た構成になっていたが、幕切れは大学生2人の軽口で終わっていた。前2作も面白いのだが、今回、ホーリーさんの心の闇に焦点が当てられたこと、それを劇場の闇とつなげたことで、格段に劇世界は深さを増した。ぜひ今後も作り変えていってほしい。また違う「レディカンヴァセイション」の世界を見てみたいと思っている。
(1)FOペレイラ宏一朗『レディカンヴァセイション(リライト)』上演台本、6頁。
(2)同上、9頁。
主な参考資料
FOペレイラ宏一朗『レディカンヴァセイション(リライト)』上演台本。
FOペレイラ宏一朗『レディカンヴァセイション』上演台本(短篇『レディカンヴァセイション』も収録)。
『レディカンヴァセイション(リライト)』当日パンフレット